笹倉 明
作家。1948年(昭和23年)兵庫県西脇市生まれ。
早稲田大学文学部卒業後、広告代理店勤務、フリーの雑誌記者を経て、『海を越えた者たち』で 第4回すばる文学賞佳作、『漂流裁判』で第6回サントリーミステリー大賞、『遠い国からの殺人 者」で第101回直木賞を受賞。「ルアン 歳月」「新・雪国」「旅人岬」「ほのおの保育 物語一広岡キミヱの足跡と生涯」など著書多数。

|
ささくら・あきら 笹倉 明 作家。1948年(昭和23年)兵庫県西脇市生まれ。 早稲田大学文学部卒業後、広告代理店勤務、フリーの雑誌記者を経て、『海を越えた者たち』で 第4回すばる文学賞佳作、『漂流裁判』で第6回サントリーミステリー大賞、『遠い国からの殺人 者」で第101回直木賞を受賞。「ルアン 歳月」「新・雪国」「旅人岬」「ほのおの保育 物語一広岡キミヱの足跡と生涯」など著書多数。 |
 |
ある歯科医の為になる話
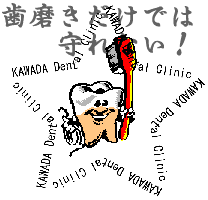 そもそも、歯石とは何ぞや。広辞苑をひもとくと、『歯牙の表面、とくに歯頸部に、唾液中の
石灰分が付着したもの。歯塩』とある。河田君の説明によれば、例えば鐘乳石のような石灰質の
沈殿物と考えればよいとのこと。専門家の間では、沈着という言葉をつかい、歯の頚の部分、つ
まり歯茎と歯の間に付着するので、歯磨きだけでは取れないものらしい。
そもそも、歯石とは何ぞや。広辞苑をひもとくと、『歯牙の表面、とくに歯頸部に、唾液中の
石灰分が付着したもの。歯塩』とある。河田君の説明によれば、例えば鐘乳石のような石灰質の
沈殿物と考えればよいとのこと。専門家の間では、沈着という言葉をつかい、歯の頚の部分、つ
まり歯茎と歯の間に付着するので、歯磨きだけでは取れないものらしい。
それがたまってくると、歯茎に炎症を起こし、出血し、膿が出、悪臭を放つばかりか、歯を支
える骨が破壊されていく。歯がグラグラになるのはそのためで、私の奥歯のズキンはまだ軽度だ
から救いようがあった。即座にマスイをかけ、歯科衛生士の女性によって歯石の除去作業が行な
われたのだったが、実は、これをやってくれる歯科医師というのは極めて少ないらしいのだ。
つまり、ほとんどの歯科医は、転ばぬ先の杖をついてくれない。転んだ人を助ける仕事が主で
あり、実際、そういう手遅れの患者しかこないせいでもあるのだが、歯の健康管理のための処置
を積極的にすすめる歯科医はきわめて少ないらしいのだ。河田君によれば、全国をみわたしても
数えるほどしかない。ゆえに、彼のところへは遠路、東京や九州からも通ってくる客がいるほど
で、インターネット上での訴えかけが効を奏しはじめた結果だという。
「みなさん、歯医者の使い方を間違っているんですよ。悪くなってからでは、もう手遅れなん
です。その他の病気とまったく同じで、もちろん治療はするけれども、どれだけよくなるかは別
問題です」
胃の痛みに耐えかねて病院へ行ったときはすでに末期でどうにもならないケースと、重度の歯
槽膿漏は同じであると考えてよい。内臓のガン検診には熱心だけれど、歯のチェックは軽くみて、
怠る人がほとんどである。従来の医師の在り方にも原因がある、そのよろしくない傾向に、彼は
率先して異議を申し立てているわけだ。
幸いにして、私の場合、マスイの痛みだけを我慢して歯石をとってもらった結果、ときにズキ
ンと痛んでいた奥歯がウソのように鎮まった。これは不思議というか、嬉しいかぎりなのである。
「それを守っていただけると、先輩の歯は、同世代の人のより十年も若いですから、八十歳ま
でいまの歯を維持できますよ」
何とも意外な言葉を聞いた。レントゲンを撮ってみた結果、骨の消耗が五十代前半にしては少
ないのだという。よく使う奥歯の一つだけ、グラツときて痛みを発生させていたけれど、その他
の部分は大丈夫、かなり強固であるらしい。
それでも虫歯があちこちにあるというのだから、これはもう転ばぬ先の杖をドンとついてもら
うしかない。二度日の訪問時から、それははじまった。
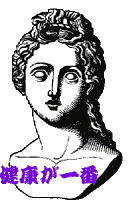 一体どこに虫歯などあるのかという私に、河田君は、
一体どこに虫歯などあるのかという私に、河田君は、
「ちょっと鏡でみせてあげて」
と、衛生士に命じた。
二つの鏡に適当な角度をつけてみせられたのは、右上の前歯の裏側だった。ちょうど前から奥
へのコーナーに当たっていて、これにはまた驚いた。
これが「死角」というものか。本人にみえないのはむろん、歯磨きでも角度的にいちばん手薄
になるところなのだ。いやはや、参ったというほかはない。
放っておくとどうなるかは、私にもわかっていた。左の奥歯でそれを経験しているからで、忘
れもしない、フランスでの取材中、我慢をしてきた痛みがついにフランスパンもかじれなくなり、
帰路に立ち寄ったフィリピンでついに限界に達し、駆け込んだ歯医者で二者択一を迫られた。
まるごと抜いてしまうか、神経を抜く治療をほどこすか。
迷わず前者を選んだ。滞在日数が限られていて治療に時間をかけられない事情もあったが、一
刻も早くこの痛みから解放されたいという願いからだった。そして、マスイ、抜歯、となる。
ゴキッと鈍い音を立てて極太の奥歯が抜ける感覚はいまも忘れないが、それよりも、抜けた歯を
みせてもらって、ヘーッと驚嘆した。その惨状を何と形容すればよいのか、ジャガイモが鼠にか
じられたような、とでもいうべきか。ごっそりと上から下まで歯の半分近くがえぐりとられてい
るのをみて、さすがにゾッとした。
左利きの私は、モノを噛むのにも左の奥歯ばかりを使っていたことから、集中的に痛みつけて
きた結果だったが、それにしても虫食いの恐ろしさは骨身にしみた。以降、右の奥歯ばかりを酷
使してきたから、ズキンときたときは、てっきりまた虫歯かと勘違いしたのだ。実は歯槽膿漏の
初期で、どうにか助かったという次第なのである。
 |
| 本文は、“BanCul 2003年 春号に 掲載されたものです。” BanCul No47,91-93,2003. |